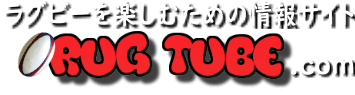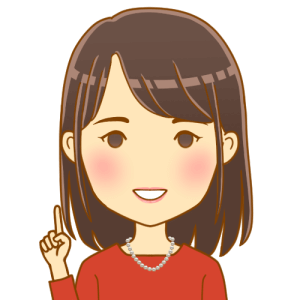
と感じるかもしれんないが、現実は甘くない。むしろ、どれだけ日本代表が強くなっても、どれだけラグビーができる環境を提供しても、それだけでは日本のラグビー人口を増やすことは難しいのかもしれない。
どうやら、日本の年代別ラグビー人口を鑑みると普及には、日本ラグビーが掲げる2021-2024中期計画 普及・育成の項目にある指導者の質向上を進める必要がありそうだ。
既にラグビー協会がイベントを開催し普及に努めているが、さらにプラスして現場に入り込みチームの子供達の生の声を吸い上げ、競技人口を維持するためのを方策を検討すべきでは?と考えている。
ココがポイント
実際に、指導者への教育や共有は行っていても、それがどのように現場に活かされ、子供たちがどのように感じているかまではフォローできていないのが現状。
このページでは、特に小中学生の指導者にフォーカスしてラグビー人口の現状と問題点についてお伝えしていきたい。
スポーツ人口

健康な体を維持するうえで、適度に体を動かすことは健康を維持するうえで必要不可欠である。高齢化が進む日本では、テニスやゴルフ以外に60代、70代の方が休日にサッカーを楽しむ光景もよく目にするようになってきた。
もちろんラグビーでも、60代、70代の方がOB戦に出場することもある。若き日のプレーを思い出し体を張る人生の先輩達には勇気をもらえる。
しかし、一方で各スポーツ競技において年々競技人口が減少傾向にあることが課題となっている。
日本のメジャー球技人口(選手登録数)
それでは、日本のメジャー球技スポーツの人口について見ていこう。
| 選手登録数 | 時点 | 情報元 | |
| バレーボール | 40万人 | 21年度 | JVA |
| サッカー | 83万人 | 21年度 | JFA |
| バスケットボール | 55万人 | 21年度 | JBA |
| ハンドボール | 10万人弱 | 20年度 | JHA |
| 野球 | 50万人弱 | 参考サイトa 、参考サイトb | |
| ラグビー | 9万人 | 21年度 | JRFU |
上記は選手登録の数字のため愛好者を含めると更なる競技人口となるが、近年日本の球技スポーツの問題点として挙げられるのが野球人口の減少。野球、サッカーの2トップだった競技人口も近年はサッカー選手数との差が広がっている。
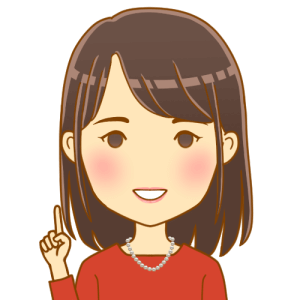
ラグビー人口は、ゴールデンの民法で多数放映されるメジャースポーツでありながらハンドボールと同じ人数レベルとなっている
日本の個人スポーツ人口(選手登録者数)
| 選手登録数 | 時点 | 情報元 | |
| テニス | 1万人 | 21年度 | 参考サイト |
| 弓道 | 12万人 | 18年度 | 参考サイト |
| 柔道 | 12万人 | 19年度 | 参考サイト |
| 空手 | 53万人 | 20年度 | 参考サイト |
| ゴルフ | 520万人(愛好者含む) |
テニスは、趣味・運動として楽しんでいる方は多いが選手として活動している人数は約1万人。
ココがポイント
設備・環境の問題から趣味では活動しにくい弓道の登録者数は凄い!民法ゴールデンで放映されるスポーツではないが、団体競技のラグビーより選手登録数の方が多い
世界のラグビー人口
では、世界のラグビー人口はどれくらいいるのだろうか。以下の表を見ると総人口に対する日本のラグビー人口が非常に少ないことがわかる。一方で、ラグビー王国ニュージーランドの人口に対する競技数の割合はやはり非常に高い。
| 競技登録者数 | 人口 | |
| 南アフリカ | 63.5万人 | 5,670万人 |
| イングランド | 35.5万人 | 5,560万人 |
| オーストラリア | 27.2万人 | 2,500万人 |
| フランス | 25.8万人 | 6,700万人 |
| ニュージーランド | 15.6万人 | 470万人 |
| ウェールズ | 10.8万人 | 300万人 |
| アイルランド | 9.4万人 | 470万人 |
| アルゼンチン | 12.1万人 | 4,420万人 |
| 日本 | 9.2万人 | 12,620万人 |
日本ラグビー人口推移
それでは、日本のラグビー人口について詳細を見ていきたい。まずはラグビー人口がどのように推移しているのか見ていこう。
日本のラグビー人口の推移を見てみると、ワールドカップが日本で開催された2019年に一時的にラグビー人口が増加しているが、コロナの影響もあり5,000人レベルで人員減となっている。
| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
| 選手登録者 | 95,042人 | 9,6713人 | 9,1861人 | 91,865人 |
せっかく日本代表が活躍し日本にラグビー旋風を巻き起こしたのだが、その後の人数減は非常に残念な結果だ。そして、日本のラグビー人口の語るうえで是非注目して頂きたいのが、年代別のラグビー人口だ。
日本年カテゴリー別途ラグビー人口
以下の表はラグビースクールに所属する小中学生の人数に特化した人員数だが非常に興味深い数字となっている。(データベース)
| 6歳〜12歳(小学生) | 12歳〜15歳(中学生) | |
| 18年度 | 19,609人 | 5,265人 |
| 19年度 | 22,346人 | 5,528人 |
| 20年度 | 24,693人 | 5,928人 |
| 21年度 | 25,282人 | 6,583人 |
総人数として減少している一方で、小学生のラグビー人口は18年度から増えている。恐らく日本代表の活躍の影響が大きいだろう。しかし、入団テストなどなく入部へのハードルは低いにも関わらず小学生⇨中学生の減少幅が大きいのはお分かり頂けるだろうか。
ココに注意
ざっくり約▲2万人(7割)がラグビーから離れている。。
きっかけ
日本代表の勇士をテレビで見る
スクールに入る
近所のスクールに通うのがほとんど。
小学⇨中学
7割の子供が、何かを理由にラグビーから離れる。
高校⇨大学や、大学⇨社会人は、続けたくても能力的に進むことができない選手がいるため、ある程度の人数減はあって当然だが、中学生に上がるタイミングで自主的にラグビーから離れているのだ。
なぜ小学生でラグビーをやめてしまうのか?指導者の責任?

数字から見ても問題点としてフォーカスを当てるとすると小⇨中の下落幅。
ココに注意
この人数減については、小中一貫のスクールが多いため、スクール全体の問題としてとらえる必要がある。
指導者・スクールは中学に進まなかったことに対して、

と本気で考え改善していく人はわずかな人数だろう。だからこそ、何年も同じ人数構成が続いている。
筆者が小学でラグビーをやめた数人にラグビーをやめる理由についてヒヤリングすると、以下の回答があった。
①楽しくない。⇨うまくならない。
②コーチが嫌い。⇨怒る・うるさい、中学の指導員が苦手
③他のスポーツがやりたい⇨楽しくない。
④土日遊びたい。
⑤親の意向。
⑥部活やりたいから中学はアカデミー、高校からまた始める。
①〜④はチームの自助努力で取り込める可能性は充分にある。欲を言えば⑤親の意向も含めて、中学生になってもラグビーと向き合ってほしい。そもそも令和の時代、人間関係ができていないのに怒鳴るというのは問題外。
もちろん怒鳴られる子供は、ラグビーを続ける子にもいるが、別に気にしてない。言われている事は覚えていない。というのが現状。子供たちの方が大人なのかもしれない。
また、⑥の選手はラグビーでは強化できないスキルを他のスポーツで強化し高校からまたラグビーを再開するという強い意志を持っている子供だが、中学ラグビーでのレベルアップも期待できないというのも理由としてある。
小学生高学年や中学生の子供たちが求めている環境
もちろん、他の考えもいるかもしれないが、ラグビーが好きな子供たちの多くは以下のような考えを持って練習に励んでいる。
やりたい事をチャレンジしたいし、自分達が考えた練習をやってみたい!試合でチャレンジしてみたい。と考える子供達は多い。結果、上手く行かなくても次の考えが生まれる。そして成功体験につながる。
ワールドカップでの日本代表の勇姿。
彼らの活躍、トップを経験した選手に教わりたい。昔と違いリーグワンのプロ化など、ラグビー選手に憧れる子供が増えてきている。レベルの高い環境でラグビーがしたい。リーグワンが運営するラグビーアカデミーに通う子供達が増えている。
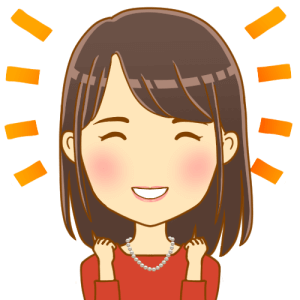
との声もあるが、アカデミーはスクールとの共存。選手を奪い合ったり競いあう事は方針ではない。
補足
休日はスクール、平日にラグビーアカデミーというスケジュールが、令和の小中学生ラガーマンのスタイルとなっている。
では、ラグビースクールに通うと子供達が理想とするチームは存在するのだろうか。ラグビースクールは大きく以下の指導レベルのチームが存在すると考えている。
| チーム | 指導レベル | 指導方針 |
| A | 低い | 自主性、個人の成長 |
| B | 高い | 自主性、個人の成長 |
| C | 高い | 勝利主義 |
| D | 低い | 勝利主義 |
基本的に、小中学生のレベルではどこのチームにいっても練習内容はほとんど同じ。どの練習に重点をおき、どのように指導を行うかでチーム力に差がでてくる。
チームの弱み強みを把握しているため、指導ポイントが的確で(親御さんも)納得できる。
ダメな理由と改善策をアドバイスできる。
時間の使い方が上手い。
怒鳴らない。気持ちの持ち上げ方が上手い。
レベルの低い指導者とは上記の真逆。
また、チームにはそれぞれ基本方針が存在するが、基本的に練習内容と直で繋がっていないチームがほとんどだ。
こんな点
例えば、チームの方針に「自主性」という項目があっても、コーチが言われと通りにプレーしないと怒られるチームも少なくない。
では、4つを一つ一つ見ていこう。
仲良しクラブという言い方が良いかは別として、
みんなで集まって楽しくラグビーで汗をかきませんか?
という感じのスクールだ。
勝つ事は優先せず、ラグビーが出来る環境を提供している。指導者も、昔ラグビーやったことあります。というお父さん達が多く、ごく一般的な練習で汗を流す。指導方法も、終始優しい雰囲気だ。
例えば、絶対にボールをパスしない子供達に対して

と無理やりという雰囲気ではない。たまに試合になったら熱くなる指導者や練習をしていないことを試合で要求する指導者もいるが、プレーに対して怒鳴ることはない。もちろんふざけている子供に対してはきつく怒鳴る(怪我が心配なため)
ただ、基礎練習が多く試合に勝ちにこだわる練習は少ない。そのため試合に勝ちたい子供や親御さんはチームに入ってから不満を感じることも少なくない。
親御さんにとっても、是非入部させたいチームだ。指導レベルが高いため、個人個人が、成長するスピードも他のスクールに比べ早い。

という成功体験を、作ってくれる。まさにenjoyラグビー。
・試合に勝てたのは選手達の頑張りのおかげ
・試合に負けたのはコーチの責任として捉えているため、スタッフは常に改善に努める
練習を見ても、「いい練習やってるなー」と感じるチームだ。チームの雰囲気もよく選手⇄指導者のコミニケーションも多く取れている。
文字通り、勝つ事を目標に練習を頑張っているチームだか、少々問題なのが、選手よりもコーチ陣の勝ちたい熱が強いという点だ。
練習で怒鳴る事は多いため萎縮してしまう選手もいる。試合に勝てないのはお前達の実力不足!チームとしては競合チームに位置づけられるため、部員数も多い。部員数が多いという事は、必然的に運動神経が良い子供も多いため、高いレベルで練習を継続していれば結果はついてくる。
Aチームの試合に出て活躍する選手でラグビーから離れる子は少ないが、ラグビーから離れたいという選手もゼロではない。また、怒られてばかりの試合に出れない子供達は、ラグビーを続けることを選ぶだろうか。
ポイント
高いレベルで練習できるが試合に出れない子のモチベーションを維持するのが非常に難しい
4つの分類の中でまたで一番改善が必要なパターンと考えてる。また、小学生でラグビーをやめてしまう原因の多くはこのようなチームで6年間を過ごした選手が多いのではないかと想定している。
全国のラグビースクールを見たわけではないためはっきりとは言えないが、人数の下落幅を見るとそう考えるしかない。
この手のチームは、昔から同じ指導者が同じ練習、同じ指導方針を続けているチームが多い。新しい風を吹き込もことに抵抗があるため、ラグビールールの変化、近代っ子の考え方にあまりついていけていないケースだ。
また、ラグビー指導レベルも高くないため、子供達のラグビースキルとしての成長は期待できない。もちろん、体の成長によりコンタクトプレーが強くなる、足が速くなるなどはある。
怒鳴る事はごく普通、
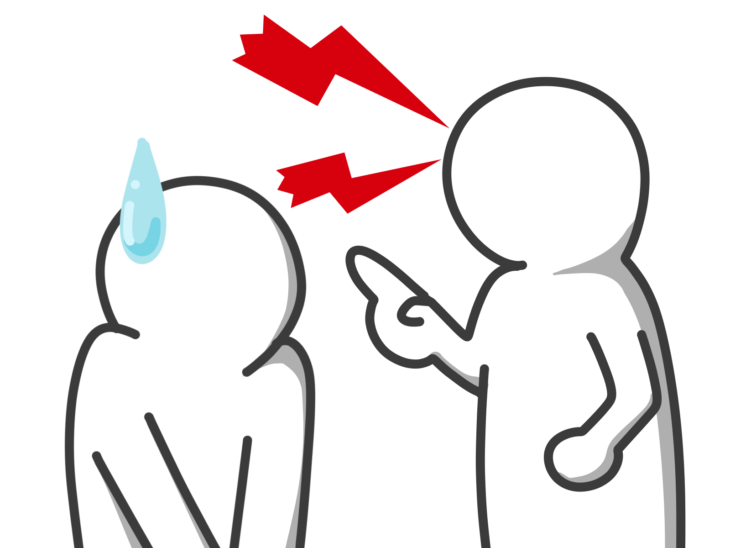
「そうじゃねーだろ!
「言われたことやらないなら教えてあげねーぞ!」
ということも平気にいう指導者が存在する。子供のプレーに対して文句を言うが、なぜその考えがダメなのか、改善策は何なのかを丁寧にアドバイスすることはできない指導者もいる。
筆者の知人の中学生に、親から新しいラグビーボールを買ってもらい喜んでいる子のエピソードを1つ紹介したい。
その子は、公園でキックの練習をするんだと楽しそうに話していたが、公園で見かけることはなかった。親御さんに利用を聞くと、「○○はキックを蹴るポジションじゃないからキックの練習しなくていい」とチームの指導者から言われたようだ。
それを聞いてびっくりした!
そんな指導者が今もいるのか。日本ラグビー協会はそのような指導者が存在する事は把握できていないのだろう。悲しいけど、これが日本ラグビーの現実だ。
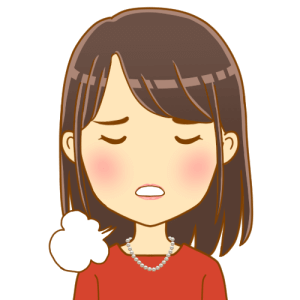
となるかもしれないが残念ながら他のチームの実情もよくわからないため簡単に選べない。
また、上記のような指導者は、選手の意見を聞かずに昔からのこだわりに固執することが多い。以下のような例を挙げたい。
メンバーを組むにあたり、縦割りにして平均的な強さを保つチームと、一軍・二軍に分けて練習や試合を行うチームが存在する。どちらもメリット・デメリットはある。
| メリット | デメリット | |
| 縦割り制 | ・スキル高い子と試合に出れる ・スキル低い子のモチベーション維持 |
・勝てるチームに勝てない。 ⇨スキル高いこのモチベーション ・下手な子は気持ち折れることも ・練習が常にレベルが高い子基準 |
| 一軍・二軍制 | ・最強チームで試合に臨める ・競争心 ・レベルにあった練習可 |
・一軍で出れない子のモチベーション維持 |
正解はないが、一軍・二軍制が良い場合もある。確かに二軍以下の子供達のモチベーション維持というのは課題としてあるが、小中学生のうちはレベルに合った指導が重要と考える。
スキルが高い子に合わせるのではなく、基礎がままならない子供にはしっかり時間をかけて基礎を指導しても良いのではないだろうか。
既にスキルが充実している選手にとっては、メリットかもしれないが、個人スキルやラグビー知識が少ない中で戦術を叩き込まれるケースだ。
さらに詳しく
近代ラグビーでは、ポットスタイルやバックドア・フロントドア等の戦術
日本代表やリーグワン、また競合チームの戦術の真似だ。
ココに注意
ラグビーの知識や試合数が少ない子供達は、動きを忠実に守り、言われた通りにポジショニングしその戦術をやりきるが、戦術をやり切ることが目的となってしまう選手も多い。
筆者が相談を受けた中学生の例を1つ紹介したい。
2次、3次 攻撃時のフォワードの動き方について相談され、色々な例を紹介している際に以下のようなやりとりがあった。





悲しくなるやりとりだった。
彼らは目的を理解せずに戦術を言われた通りにやりきるだけのロボットになっていた。
そして、戦術が通用せずに負けてしまえば、来年は違う戦術で挑戦することもある。戦術の前に子供達が高めるスキルは山ほどある。
超シンプルな戦術でも試合に勝てる!ラグビースキルは十分か?

小中学生のコンタクトレベルであれば、戦術やサインプレーがなくても試合に勝つことは十分に可能だ。基礎スキルやスキル個々の精度を高めることの優先度を高めたい。
①パスの精度
②コンタクトスキル・強さ
③ボールをもらうときのスピード
④スタミナ
⑤タックルポイントへのよりの速さ
⑥スピードのコントロール
⑦タックル精度 などなど
ラグビー選手として活躍していくうえで追及すべきことはたくさんある。しかし、その精度もままならないまま戦術を追及する傾向にあるチームも少なくない。
そして、もう1つ重要視したいのがディフェンスの練習量は足りているかという点。アタック9割・ディフェンス1割といった練習量のチームも多い。1対1のタックルを練習しただけでどうにかなるスキルではない。
ラグビーの名言に、

とあるように、1点も奪われなければ負けることはないのだ。
指導者育成に向けた対応案
サッカー、野球、バスケなどのメジャースポーツと異なる点は、個人練習でスキルアップできない部分が多い点だ。敵や味方があってのスキル向上。スキル上達はキッカーの個人練習くらいだ。
さらに詳しく
そもそも親も素人が多いラグビーは、家に帰り自主練でレベルアップを図ろうとしても試合に必要なスキルを鍛えることは難しい。場所・仲間・そして指導者が必要なのだ。
育成レベル・指導方法を踏まえた評価の見える化
こんなことができららいいかも。という安易な考えかもしれないが、非常に大事なことだと感じている。
チームの強い・弱いは、保護者間の会話やホームページなど覗きにいけばある程度把握することはできる。しかし、育成方針や指導レベルまでは把握することは難しい。
・指導員のラグビー経験年数、指導暦
・小学⇨中学への継続率
・卒業生の評価
・協会の評価
上記を踏まえた、評価をホームページに掲載することを推進してみてはいかがだろうか。5つ星でも構わない。もちろん、載せる載せないはチームの自由だが、載せるチームは自信を持ったチームであることには違いない。
逆に、載せないと判断したチームも指導者が交代し方向性が変わる可能性もあるため、1回/年を更新のタイミングとし評価可否を判断してみてはいかがだろうか。
最後に
日本代表が日本中に勇気と感動を与えたのが2015年ワールドカップ、世界中の著名人を驚かせた南アフリカからの逆転トライ。そして2019年日本ワールドカップでのリーグ突破ベスト8
ラグビー日本代表はかっいい姿を我々に見せてくれた。2016年にスクールに入部した当時小学生1年生の子供達は2023年で中学生3年生。
あの時、ラグビーを始めた子供たちはラグビーやってよかったと感じているだろうか。何人が高校でラグビー続けるだろうか。
ラグビーと触れ合える環境の少なさ、ラグビーの危険性はもちろんあるかもしれない。そのためタグラグビーの普及など入口は広くなっている。

一人でも多く、ラグビーは楽しいスポーツ・やりがいを感じられるスポーツと感じ続けてもらうためには、指導者一人一人が選手個人個人と向き合い日々レベルアップしていく必要がありそうだ。