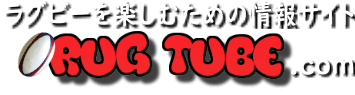ラグビーワールドカップやテレビをご覧の方は何度も耳にするよくご存じ言葉でしょうが、TMOはラグビーにおけるビデオ判定のことを言います。
このページでは、近代ラグビーの試合ではかかせないTMO(テレビジョンVBvbマッチオフィシャル)について紹介いたします。
TMOの日本導入は一足遅い
サッカーではVAR(ビデオ・アシスタント・レフリー)、アメリカンフットボールではインスタントリプレイ、野球ではチャレンジとかリクエストとかいろいろとスポーツによってビデオ判定は異なった名前で呼ばれます。
古いものだと日本では大相撲のビデオ判定が1969年から導入されたのが一番早いでしょうか。ビデオ判定はテレビ中継があり、場内に表示される大型テレビ設備が条件として必要でしたので、スーパーラグビーで2001年から、ワールドカップでは2003年から、日本国内ではトップリーグでは2014年から全試合導入されました。
サッカーが2018年ワールドカップからJリーグで2021年からなのでサッカーよりはビデオ判定の歴史はラグビーのほうがあります。野球でもビデオ判定はMLBで2008年、NPBで2018年とラグビーよりは導入が遅かったです。
どのスポーツでも審判の判断が絶対で一度決定したことは覆らないのが伝統的な歴史でした。テレビなどの映像技術が進歩した現代では映像の公平性が保たれているのでビデオにたよる判定が必然になりました。
つまり誤審がはっきり映像で残るのでそれに対応できるシステムを作ることがどのスポーツでも求められる時代になりました。
スーパーラグビーで起こったミスジャッジに対応するためにTMOは生まれました。人間的な個人差で判断が変わるよりもどの審判でも同じ判定が機械的にされる傾向が好まれ、証拠として映像で検証することが即時にできる機器が開発されたのです。。
しかし従来の判定方法を変えたくない保守的なスポーツが多い中ラグビーはよりスピーディーでスリリングなプレーに対応するために変わっていきました。こういう点からもラグビーというスポーツは他のスポーツよりも革新的なルール改正にチャレンジしてきた結果TMOを導入したのかもしれません。
ただし、TMOは試合を止めて判定するので当初は得点にかかる判定のみ限定されていました。ビデオ判定の時間の浪費は試合を間延びさせ、選手にも観客にも良くないと思われたのですべてのプレーはできませんでしたが、最近悪質な危険なプレーの判定のみ追加されることになりました。。
TMOは選手から要求出来ない
アメリカンフットボールや野球は選手から要求されてビデオ判定されます。判定はプレー全般に適用されます。
ラグビーやサッカーなどのスポーツは審判の要求でビデオ判定されます。判定は限定的です。
特にサッカーは得点シーンや、PK、レッドカードなどの重大な見逃しや明らかな誤審だけに適用されます。ラグビーも得点に関わる不明確なプレーとイエローカードやレッドカードに関わる不正なプレーのみ適用されます。
それだけにレフリーがTMOにするかしないかを決め、ビデオ判定した後でそれでも明確でない場合は最終的にレフリーの判断に頼るので権限は依然大きいと言えます。
ラグビーの競技規則では以下に関する状況を明確にするためにTMOを指名できると書かれてます。
・インゴール内のボールのグラウンディング
・ボールをグラウンディングする動き、または、ボールがデッドになる際における、タッチ、またはタッチインゴール。
・ゴールキックが成功したかどうか、疑いがある場合。
・マッチオフィシャルが、トライにつながる、または、トライを妨げる反則が起きたかもしれないと考える場合。
・不正なプレー。罰の確定を含む。
言い換えると
・キックで転がったボールを押さえてトライできたか?
・ボールを落としていないか?
・体がタッチに押し出されていないか?タッチインゴールから出てないか?
・ボールと地面の間に防御側チームの選手が入っていないか?どちらが押さえたか?
・ボールが地面に接して押さえているか?
・ドロップゴールがゴールポスト内にキックが入っているか?
・トライに関わるプレーでスローフォワードやオフサイドなどの反則をしていないか?
・ハイタックルなどの危険なプレーでイエローカードやレッドカードにあたる重大な反則を査定するとき。
レフリーが必要と判断した時に手で四角形を描きます。それからTMOによる判定が始まります。別室のビデオ係に無線で確認項目を連絡します。
TMOがチェックしてレフリーが目視して判定した内容を覆す判定があればレフリーに伝えるのがTMOの役目です。ビデオ操作はホークアイ社のビデオレビューシステムを使って最近ではテレビ制作会社の補助なしでTMO自らの操作で判定しています。
ほとんどの場合スタジアムの大型モニターでリプレイの内容は確認できます。ビデオ操作のスキルや判定の無線のやり取りがスタジアムではわかりにくいなど改善点はありますが、おおむね運用できています。
TMOで明確になる危険なプレー
危険なプレーのビデオ判定は近年から厳しく判定するようになりました。危険なプレーは審判の目視だけでは見落としやすく、適正な判定が難しいです。特にハイタックルなどの危険なプレーはビデオで確認して判定されてます。
例えばハイタックルではインパクトの位置の高さが肩より上か、危険性、故意か偶然かなど査定します。それによって普通のペナルティか、警告するべきペナルティか、イエローカードか、レッドカードかを判定します。
危険なプレーを判定するときは、ラフプレーなどで一触即発の荒れた場面も多いのでTMOの間が荒れた場面を鎮める効果もあるので、判定を即断するよりもTMOで確認するべきでしょう。シンビンや退場は戦力を変えてしまう大きな判定です。試合の時間は間延びしますが、選手のためにも慎重な判定を審判はしてほしいものです。
リーグワン第4節でも上述のような場面がありました。BL東京vsトヨタVで後半25分トヨタヴェルヴリッツの福田健太選手が抜け出し、ブレーブルーパス東京のセタ・タマニバル選手が背走してタックルした一連のプレーが危険なプレー(ハイタックル)とされてイエローカードが出されてペナルティトライになりました。
一連の判定は問題のない判定とも思われます。しかし、後方から飛びついてジャージを肩より下の位置をつかんで引っ張って押し倒したのでハイタックルとは思えないし、襟首持って振り回す危険なプレーで納得できるのですが、TMOなしで即刻ペナルティトライに判定したので、確認するとまずい判定だったのかとも思えました。
遠くで見てるとトライセービングのタックルが決まったのになぜペナルティトライになるの?とも思えます。タマニバル選手もエキサイトしたプレーの後にイエローカード出されて怒っているので、一拍置いて冷静にするためにもTMOで検証してからペナルティトライの流れにするほうがレフリングの公正さが保たれると思います。
TMOになるプレーはキックパスを使ったスリリングな紙一重のグラウンディングの攻防、タッチライン際の激しい攻防、スローフォワードギリギリのパスプレー、ゴールラインを超えるか超えないかの厳しいモールの攻防などラグビーの醍醐味が詰まってます。
日本国内のTMO映像は歴史も浅くあまり見かけませんが、YouTubeでTMOを検索すると次のような面白い世界のラグビー映像が見れます。
TMO判定がラグビーを面白くする
・あとちょっと…!トライにならなかったトライ集トップ5
・To TMO or not TMO
ミスジャッジをなくすためにTMOが生まれて20年経ちました。大型モニター施設や映像システムのデジタル化や無線技術の進化で映像のリプレイ検証も容易になりました。
映像の解像度や解析の技術革新が進めば、よりスムーズに判定できるようになるでしょう。現状はレフリーの判断にかかるところが大きいです。
レフリーの技術はルールの把握だけでなく、TMOを使うタイミングやTMOのビデオ操作など多岐にわたり負担も大きいです。TMOをすべて機械化して判定できないので、最終的に人間の判断で決めます。
TMOがあることでいままで流されていた反則もわかるようになりました。レフリーだけでなく選手やファンがルールをいつまでも守っていく、ラグビー憲章の一つである「規律」の順守が必要ですね。